
血液のがんって、白血病のほかに何があるの?

血液のがんはたくさんの種類がありますよ。
それぞれに特徴があり、治療も全然違うんです。
平均寿命が伸びている日本では、血液のがんにかかる方も増えてきています。
今回は血液専門医のつかポンが血液のがんについて詳しく解説させていただきます。この記事を読めばそれぞれの病気の特徴がわかると思います。
ではよろしくお願いします。
1. 血液疾患とは

血液には赤血球、白血球、血小板などの血球や血を固める役割の凝固因子などが含まれています。
また血球は血液の工場である骨髄(こつずい)でつくられます。骨髄では血球の赤ちゃんである造血幹細胞(ぞうけつかんさいぼう)からすべての血球がつくられています。
血液疾患とは、血球や凝固因子に異常が起こる病気を指します。
主な症状は以下の通りです。
- 赤血球が減る → 貧血になり息切れや動悸、疲れやすさを感じる
- 白血球が減る → 感染しやすくなり熱が出る
- 血小板や凝固因子が減る → 出血しやすくなる
血液の病気は大きく、がんとそれ以外の病気に分けられます。
1-1. 血液のがん

がんとは、正常な細胞の遺伝子が傷ついてできた異常な細胞が、どんどん増えつづける状態をさします。
白血病、骨髄異形成症候群(こつずいいけいせいしょうこうぐん)、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫(たはつせいこつずいしゅ)、骨髄増殖性腫瘍(こつずいぞうしょくせいしゅよう)などは白血球のがんです。
血液のがんといってもその症状や治療法はさまざまです。その理由は、がんになる血液の細胞が病気によって違うからです。
1-1-1. 血液のがんの治療
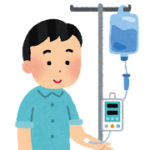
病気によって治療法は異なりますが基本は抗がん剤で寛解(かんかい)、完治を目指します。
時に放射線療法を併用したり、造血幹細胞移植(ぞうけつかんさいぼういしょく)を行ったりします。
1-2. 血液のがん以外
がんではない血液の病気もたくさんあります。
鉄不足による鉄欠乏性貧血、血小板が減る特発性血小板減少性紫斑病(とくはつせいけっしょうばんげんしょうせいしはんびょう)、出血しやすい血友病(けつゆうびょう)などがそうです。
今回は血液のがんについてそれぞれ説明していきます。同じ病気でも患者さんによって治療は違うので、詳しい事は主治医の先生に確認しましょう。
2. 【病気の解説】主な血液のがん
2-1. 白血病
白血病には① 急性骨髄性白血病 ② 慢性骨髄性白血病 ③ 急性リンパ性白血病 ④ 慢性リンパ性白血病の4種類のタイプがあります。
2-1-1. 急性骨髄性白血病(Acute Myeloid Leukemia : AML)
- 概要
AMLは未熟で役に立たない骨髄系の血液細胞(芽球)が増え続ける病気です。
骨髄で芽球が増えると正常な血球がつくられなくなり、出血、感染によって致命的な経過をとります。
- 症状
正常な血球が作れなくなることにより貧血による息切れや動悸、白血球減少による感染症の発熱、血小板減少による出血が主な症状です。
時に肝臓、脾臓、中枢神経(脳、髄膜)、歯肉、皮膚などで白血病の細胞が増殖(浸潤:しんじゅん)することがあります。お腹の張り、頭痛などの神経症状、歯肉の腫れ、皮疹などを認めることがあります。
- 診断
血液検査と骨髄検査で白血病細胞の増殖を確認します。治療法を選ぶために顕微鏡での細胞の形、染色体検査、表面マーカー検査、遺伝子検査なども行います。
- 治療
入院での早急な治療を行います。治療は抗がん剤を組み合わせた化学療法です。化学療法を繰り返し、完治を目指します。再発したり、通常の治療が効かない場合は造血幹細胞移植を考えます。
2-1-2. 急性リンパ性白血病(Acute Lymphoblastic Leukemia : ALL)
- 概要
ALLは未熟で役に立たないリンパ系の血液細胞(芽球)が増え続ける病気です。
骨髄で芽球が増えると、正常な血球がつくられなくなり、出血、感染によって致命的な経過をとります。
小児に多く、大人では稀で1年間の発症率は10万人に1人程度といわれています。
- 症状
正常な血球が作れなくなることにより貧血による息切れや動悸、白血球減少による感染症の発熱、血小板減少による出血が主な症状です。
リンパ節、肝臓、脾臓で白血病の細胞が浸潤することがあります。特にALLでは中枢神経に浸潤する事が多く、頭痛や麻痺などの神経症状などを認めることがあります。
- 診断
血液検査と骨髄検査で白血病細胞の増殖を確認します。治療法を選ぶために顕微鏡での細胞の形、染色体検査、表面マーカー検査、遺伝子検査なども行います。
特にフィラデルフィア染色体という異常な染色体が見られるかどうかで治療方法や予後が大きく変わります。
また脳脊髄液検査を行い、中枢神経への広がりを調べます。
- 治療
入院での早急な治療を行います。治療は抗がん剤を組み合わせた化学療法です。化学療法を繰り返し、完治を目指します。再発したり、通常の治療が効かない場合は造血幹細胞移植を考えます。
2-1-3. 慢性骨髄性白血病(Chronic Myeloid Leukemia : CML)
- 概要
CMLは血球の赤ちゃんである造血幹細胞の遺伝子に異常が起こり、成長した大人の血球(特に白血球)が必要以上に作られる病気です。
さらに放置すると細胞の成長も止まり、未熟で役に立たない血液細胞(芽球)が増加する急性期に移行します。急性期に移行したCMLは予後が極めて不良です。
- 症状
多くの方は症状はなく、健康診断や他の病気の検査中に偶然に発見されることがほとんどです。
急性期に進行すると、貧血・感染症・出血など急性白血病と同じ症状がみられます。
- 診断
血液検査と骨髄検査で白血球の増加を確認します。慢性骨髄性白血病に特徴的なフィラデルフィア染色体という異常な染色体が見つかれば診断が確定します。
- 治療
CMLを治すことは難しいですが、長期にわたって病気をコントロールすることは可能です。
慢性期の治療はチロシンキナーゼ阻害薬という分子標的薬を内服します。
急性期の治療はチロシンキナーゼ阻害薬だけでは効果が不十分なため、抗がん剤による治療(化学療法)や造血幹細胞移植を検討します。
2-1-4. 慢性リンパ性白血病(Chronic Lymphocytic Leukemia : CLL)
- 概要
CLLは成熟したBリンパ球が増え続ける病気です。
非常に進行がゆっくりな病気で、50歳以降の中高年に多く男性に多いのが特徴です。
欧米では最も頻度の高い白血病ですが、日本では稀な病気です。日本での1年間の発症率は10万人に1人未満といわれています。
- 症状
CMLと同様に自覚症状がないことが多く、健康診断や他の病気の検査中に偶然に発見されることがほとんどです。
病気が進行するとリンパ節、肝臓そして脾臓でも増殖するので、リンパ節の腫れやお腹の張りを認めることがあります。また貧血・感染症・出血などの症状がみられます。
- 診断
血液検査で成熟Bリンパ球の増加を確認します。表面マーカー検査でCLLに特徴的な細胞表面(CD5とCD23という蛋白質)で確定します。次に骨髄検査やCTで病気の広がりを確認します。
- 治療
CLLを治すことは難しいですが、長期にわたって病気をコントロールすることは可能です。
ゆっくりと進行する病気なので、治療を開始するタイミングは症状の有無、CLL細胞の数、血球減少の程度を総合的に見て決めます。
治療は抗がん剤を組み合わせた化学療法や分子標的薬の内服を行います。
2-2 骨髄異形成症候群症候群(Myelodysplastic Syndrome : MDS)
- 概要
MDSは血球の赤ちゃんである造血幹細胞の遺伝子に異常が起こり、血球の成長が上手くいかず血球減少が起こる病気です。また未熟で役に立たない血液細胞(芽球)が増え、急性骨髄性白血病に移行する場合があります。
MDSは単一の病気ではなく様々な種類があり、同じ病気でも進行の速度や特徴が変わってきます。
- 症状
多くの方は自覚症状がなく、健康診断や他の病気の検査中に偶然に発見されることがほとんどです。病気が進行すると貧血・感染症・出血などの症状がみられます。
- 診断
血液検査と骨髄検査で診断します。血液検査では血球減少を確認します。続いて骨髄検査では顕微鏡で異常な細胞の有無と芽球の割合などを調べます。さらに染色体検査、遺伝子検査などの結果を総合して診断を確定します。
- 治療
MDSの症状や病気の状態は患者さんにより様々であるため、検査結果をもとに予後予測を行います。その予後(リスク)や病状に応じて治療法を決めていきます。
〜 低リスク 〜
輸血や造血ホルモンの皮下注射、免疫抑制剤や抗がん剤の内服などを行います。
症状の軽い患者さんでは、無治療で経過観察することもよくあります。
〜 高リスク 〜
年齢の若い方は造血幹細胞移植で完治を目指します。
高齢の方はビダーザ®︎やAMLと同じような化学療法を行います。
2-3. 悪性リンパ腫(Malignant Lymphoma : ML)
- 概要
悪性リンパ腫はリンパ球が増え続ける病気です。
悪性リンパ腫には100種類近くのタイプがあり、大きくはホジキンリンパ腫とB細胞リンパ腫とT/NK細胞リンパ腫に分けられます。
- 症状
痛みを伴わないリンパ節の腫れが最もよく認められる症状です。首、腋の下、足の付け根に腫れやしこりとして自覚されます。また体の中にあるリンパ節が腫れることもあります。
また臓器にかたまりを作って症状を起こすことがあります。そのほかに発熱や寝汗、体重減少を認めることもあります。
- 診断
診断や病型を確定するために生検を行います。生検では腫れているリンパ節などの病変の組織をとって、顕微鏡での細胞の形、染色体検査、表面マーカー検査、遺伝子検査などを行います。また病気の広がりを調べるためにCTやPET/CTなどの画像検査や骨髄検査などを行います。
- 治療
悪性リンパ腫の治療は悪性リンパ腫のタイプ、病期によって変わります。
治療は抗がん剤を組み合わせた化学療法や分子標的薬の内服、放射線療法などを行います。再発したり、通常の治療が効かない場合は造血幹細胞移植を考えます。
2-4. 多発性骨髄腫(Multiple Myeloma : MM)
- 概要
MMは形質細胞が増え続ける病気です。
形質細胞は免疫グロブリンと呼ばれる蛋白を作り細菌、ウイルスなど体内に侵入してきた異物を攻撃します。増殖する形質細胞(骨髄腫細胞)から産生される免疫グロブリンをM蛋白と呼びます。
高齢の方に多い病気です。
- 症状
MMは形質細胞の増殖とM蛋白の増加に伴う症状がみられます。骨髄で形質細胞が増殖すると貧血・感染症・出血などの症状がみられます。
また高カルシウム血症によるめまい、頭痛、口の渇き、便秘、食欲不振、腎障害による浮腫み、骨折による腰痛などを認めます。さらにM蛋白が増加すると血がドロドロになり頭痛などが現れます。
ただし初期には自覚症状がなく、健康診断や他の病気の検査中に偶然に発見されることも少なくありません。
- 診断
骨髄検査で形質細胞の増加を確認します。また治療法を選ぶために顕微鏡での細胞の形、染色体検査、表面マーカー検査、遺伝子検査などを行います。また病気の広がりを調べるためにCTやPET/CT、MRIなどの画像検査を行います。
- 治療
MMは完治することが難しい病気です。早期治療により生命予後が改善しないため、症状がない場合には、定期的に経過観察をします。症候が出た時点で治療を開始するのが一般的です。
基本的な治療は抗がん剤を組み合わせた化学療法です。場合によって造血幹細胞移植を考えます。
2-5 骨髄増殖性腫瘍(Myeloproliferative Neoplasms : MPN)
MPNは血球の赤ちゃんである造血幹細胞の遺伝子に異常が起こり、血球がどんどん作られる病気です。MPNには大きく分けて慢性骨髄性白血病、真性多血症、本態性血小板血症、原発性骨髄線維症があります。
2-5-1. 慢性骨髄性白血病(Chronic Myeloid Leukemia : CML)
2-3-3. 慢性骨髄性白血病(Chronic Myeloid Leukemia : CML)に記載しています。
2-5-2. 真性多血症(Polycythemia Vera : PV)
- 概要
PVは主に赤血球が増え続ける病気です。
真性赤血球増加症は100万に数人の割合で発症するまれな病気で、男性に多くみられます。
予後は比較的良好ですが、長い経過の中で骨髄線維症や急性骨髄性白血病に移行することもあります。
- 症状
多くの方は自覚症状がなく、健康診断や他の病気の検査中に偶然に発見されることがほとんどです。赤血球の数が著しく増えると顔の皮膚が赤くなったり(赤ら顔)、入浴後に全身がかゆくなったり、胃潰瘍になったりします。血液の流れが悪くなり、頭痛、耳鳴り、めまいなどの症状が現れ、時に血管の中で血の塊(血栓)を作り、脳梗塞や心筋梗塞を起こすこともあります。
- 診断
骨髄検査と血液での遺伝子検査で診断します。
真性赤血球増加症では95%以上の患者さんにJAK2遺伝子変異という特徴的な遺伝子の異常がみられます。
- 治療
PVは治すことができない病気です。病気をコントロールし、上手く付き合っていく必要があります。
PVでは血栓症が起こらないように赤血球の数を減らす治療(瀉血(しゃけつ))を行います。瀉血とは血液を1回に200-400ml捨てる治療です。しかし瀉血が頻回、血栓症の既往がある、60歳以上の高齢者である場合には内服の抗がん剤(ハイドレア®︎)で赤血球数を低下させます。
また血栓が出来にくいように生活習慣の管理(タバコ肥満、高血圧、脂質異常症、糖尿病)と血液をサラサラにする抗血小板薬(バイアスピリン®︎)の内服も行います。
2-5-3. 本態性血小板血症(Essential Thrombocythemia : ET)
- 概要
ETは主に血小板が増え続ける病気です。100万に数人の割合で発症するまれな病気で女性に多くみられます。
予後は比較的良好ですが、長い経過の中で骨髄線維症や急性骨髄性白血病に進行することもあります。
- 症状
多くの方は自覚症状がなく、健康診断や他の病気の検査中に偶然に発見されることがほとんどです。血小板の数が著しく増えると、血栓ができやすくなり、PVと同じ症状を起こすことがあります。一方で血小板が増えすぎることで、逆にその機能が低下し出血しやすくなります。
- 診断
骨髄検査と血液での遺伝子検査で診断します。
ETでは50%程度の患者さんにJAK2遺伝子変異という特徴的な遺伝子の異常がみられます。
- 治療
ETは治すことができない病気です。病気をコントロールし、上手く付き合っていく必要があります。
血栓症の既往がある場合、60歳以上の高齢者である場合には血液をサラサラにする抗血小板薬(バイアスピリン®︎)の内服や内服の抗がん剤(ハイドレア®︎)もしくはアグリリン®︎を投与し、血小板の数を減らします。
2-5-4. 原発性骨髄線維症(Primary Myelofibrosis : PMF)
- 概要
PMFは特に血小板や白血球のが増え続け、その結果骨髄が線維化が進んでしまう病気です。線維化する原因により、原発性・二次性に分かれます。原発性は造血幹細胞そのものに異常が起こることで線維化が進む病態、二次性は真性多血症や本態性血小板血症などの別の疾患が原因となる病態を指します。
ほとんどの患者さんは、まず貧血(赤血球が不足した状態)になります。さらに線維化が進むと、やがて白血球や血小板も作られづらくなります。また経過中に病気の進行に伴い、白血病を発症することもあります。
- 症状
最も多いのが息切れなどの貧血症状です。またお腹の張り、腹痛など脾臓の腫れによる症状を伴うこともあります。病気が進行すると発熱、寝汗、体重減少など全身症状を伴うこともあります。
- 診断
骨髄検査では骨髄の繊維化で診断します。PMFでは50%程度の患者さんにJAK2遺伝子変異という特徴的な遺伝子の異常がみられます。
- 治療
貧血が進行した場合には赤血球の輸血を行います。脾腫による腹部症状を伴う場合にはJAK2阻害剤(ジャカビ®︎)の投与を検討します。脾臓の大きさを小さくしたり、全身の症状を改善するだけでなく、生存期間の延長が期待できます。患者さんによっては白血球や血小板が多くなることもあり、その場合には内服の抗がん剤(ハイドレア®︎)による治療を行うこともあります。
骨髄線維症の根治療法としては造血幹細胞移植があります。
ありがとうございました。血液について別の記事でも解説しているので参考にしていただけると幸いです。
Twitterでのいいねやフォローをして頂けますと大変うれしく、やる気も倍増しますので是非よろしくお願いします。
お疲れ様でしたっ!


コメント